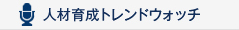人財育成に関して先進的な取り組みをしている日本IBM人財ソリューション株式会社代表取締役の片岡久氏にお話を伺いました。(インタビュー2012年8月3日、敬称略)
第1回 IBMにとって教育とは?
発明したことを広めるためには教育が必要
浦山:IBMさんは人財育成のモデルになっていると思います。一歩も二歩も先をいかれていると思います。そもそもIBM社にとって教育というのはどういう意味があって、どのように作ってきたのでしょうか。
片岡:IBMはちょうど昨年(2012年)で100周年でした。創業者のトノス・ワトソンの言葉に「教育に飽和点はない。」というのがあります。我々がビジネスをやる上で、新しいものを作る、そして、それをもとにして社会を変革していく、社会に貢献していくという考え方を意味しています。ここが原点です。
インベンションズという言葉とイノベーションズという言葉があります。インベンションというのは、エジソンのような大天才がすごい発明をする、例えば電灯を作る発明をする、その電灯で街を明るくする、それによって様々なビジネスの形態が変わる、そういったことをインベンションといいます。インベンションをやろうとしますとこれはエジソンひとりでは出来なくて、いろいろな人たちがそこに関わってくる。
その新しい発明をどう使うか、あるいはそれをやるためには何をしたらいいのか、を議論しながら作る。そして新しく出来たものを使っていこうとするときに、内容を伝えることが必要になる。それが教育です。インベンションをイノベーションにしようとする時には必ず間にエデュケーションが必要になる。
IBMは、それをビジネスのひとつのモデルにしている企業です。1932年に、初めて教育をお客様にする、ということを始めました。それは、私どもが開発をした新しいものを実際に世の中でいろんな形で使っていくため、その内容をお客様がご理解いただくためです。お客様に教育をさせていただくことでその技術が大きく広がり、社会の変革にお役にたっていく、それをビジネスとしてきたのです。
浦山:80年も近く前からですか。
片岡:そうです。IBMはビジネスのひとつのプロセスとして教育というものを捉えていたということです。
浦山:しかもお客様に対して教育するという発想があった。
片岡:そうですね。おそらく、当時の会社は社員に教育をする、そして社員はお客様のところに行って提供するということを考えていたのでしょう。その教育内容をオープンにしていく、それはIBMで今もずっと受け継がれている考え方のひとつです。DNAだと思います。
浦山:ありがとうございます。