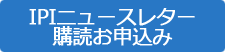モチベーションやエンゲージメントを高めることは、学習だけでなく、人間のさまざまな活動を促すための万能薬であると考えられがちです。しかし、学習科学の研究者であるPaul Kirschner氏によれば、それは過大な期待であるようです。
エンゲージメントは学習にプラスの影響を与えない
発見型学習、探究型学習は、学習者が具体的に何かを行う(「エンゲージ」する)ことによってモチベーションも高まり、それが学習効果につながることを前提としています。
しかし、ある研究によると、発見型学習を行った学習者は、平均を上回るエンゲージメントや興味のレベルを示していたけれども、実際の学習効果は平均未満でした。これは、発見型学習を取り入れれば学習効果が高まるという、教育の世界に広まっている信念に反するものです。
内発的モチベーションとその後の成績は関係ない
DeciおよびRyanによる自己決定理論(self-determination theory)によれば、報酬など外部から与えられる「外発的」モチベーションよりも、「内発的」モチベーションの方が有効だということです。
しかし、小学生を対象に、内発的モチベーションと算数の成績の関係を4年間にわたって調査した研究は、意外な結果となりました。算数に対する内発的モチベーションがあることが算数の成績を高めるのではなく、「算数の成績がよいことが、算数に対する内発的モチベーションを大きく高める」ことがわかったのです。
この研究の結果は、内発的モチベーションが学習効果につながるという広く受け入れられている考えに反しています。
発見型学習にしろ、自己決定理論にしろ、広く信じられている「ゴールデンルール」について、あらためて調査し直す時期が来ているようです。
元の記事:
関連記事:
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。