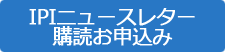Kathleen D. VohsおよびAndrew C. Hafenbrackという2人の行動科学の研究者によると、マインドフルネスの瞑想によってモチベーションが失われる可能性があるそうです。今日は、このことに関してNew York Timesに掲載されていた記事を紹介します。
マインドフルネスは仏教を由来としており、今この瞬間に完全に心を集中する瞑想を行うものです。最近の企業では、実利的な目的でマインドフルネスが広く取り入れられており、仕事への満足度、合理的試行、感情的回復力など、その実際的効果が多くの研究によって裏付けられています。
マインドフルネスの中心にあるのは、「物事をありのままに受け入れる」ことです。一方、企業としては、現状を受け入れるのではなく、より望ましい未来のためにがんばろうという「モチベーション」を従業員に期待したいところです。つまり、マインドフルネスとモチベーションは相容れない可能性があります。
マインドフルネスとモチベーションが相対するものであることを確認するための実験を行ったところ、マインドフルネス(瞑想)はモチベーションを損なうという強力なエビデンスが得られました(この結果は今後発表)。
この実験では、一部の被験者にマインドフルネスのトレーニングを受けさせ、実験の一環として瞑想を行わせました。他の被験者には、瞑想ではなく思考をさまよわせることを奨励したり、ニュースを読んだりさせました。
その後、被験者の日々の業務に近い内容のタスクを行うことに関して、そのモチベーションを尋ねる質問をします(「このタスクに対してどのくらい努力し、どのくらいの時間をかけるつもりですか?」)。
その結果、瞑想した被験者の方が、そうでない被験者に比べ、モチベーションレベルが低いことが判明しました。瞑想した人は、タスクに取り組む意欲が低く、それにかけようと思う時間も少なくなっていました。
この実験ではさらに、そのタスクの実際のパフォーマンスも測定しました。その結果、瞑想したことと、作業の質には関係がないことが明らかになりました。瞑想によって集中力が増すと言われていますが、この実験ではモチベーションレベルが低下したことによって、その利点が失われたと考えられます。
マインドフルネスが、心の静寂や受容性をもたらすということは否定できません。しかし、心の受容性が増したとしても、モチベーションが高まるわけではないのです。
マインドフルネスに関しては、この他にも、誤った記憶が形成されるなど、副作用が報告されています。詳しくは以下の関連記事をご参照ください。
関連記事:
元の記事:
https://www.nytimes.com/2018/06/14/opinion/sunday/meditation-productivity-work-mindfulness.html
学習に関して広まっている誤った考え方についての記事:
『学習スタイルの神話(learning style myth)』
『「脳に基づく(brain-based …)」学習は、事実というより虚構である』
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。