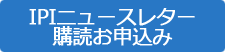これは、オンライントレーニング(バーチャルトレーニング)の専門家であるCindy Huggett氏による記事の続きです(前回の記事)。
教室型トレーニングをオンライン化する3つのステップ
教室型トレーニングをオンライン環境に転換する場合には、よくある誤り(前回の記事を参照)に注意し、以下の3つのステップに従って移行します。
ステップ1: 学習目標からはじめる
オンライン学習の場合であっても、当然、まず学習目標は何であるのかを考えます。そのオンラインコースによって、学習者が何を知り、どのようなスキルを身につけ、どのように行動が変化させる必要があるのかを考えます。そして、それぞれの学習目標について、それがファシリテーターの指導を必要とするのか、学習者がひとりで学ぶことができるのかを判断します。たとえば、学習者が事前に何かを読んでおき、オンラインクラスでは、それに基づいて話し合いなどのアクティビティを行います。
このように、教室型研修を構成する要素をブレイクダウンし、ブレンド型にすれば、オンラインでの時間を最大限に活用し、学習効果をさらに高めることができます。
ステップ2: 各学習目標に最適なアクティビティを選ぶ
学習目標を明確にしたら、それぞれに適した学習アクティビティを選びます。オンラインの場合は、教室型とは使うツールが異なります(例:チャット、投票、ホワイトボード機能、ブレイクアウトルーム、ファイル転送、注釈機能など)。ツールをさまざまに活用し、学習者をエンゲージさせます。
ステップ3: ツールや対話を使ってエンゲージする
オンライン学習の最大の利点は、そのために職場を離れる必要がないことです。しかしその一方、学習者がマルチタスク(授業を受けながらメールを見るなど他のことをしてしまう)をしてしまう可能性も高まります。これを避けるには、学習者とのやり取りを頻繁に行います。最低でも、4分に1回は、学習者と何らかのやり取りが発生するようにします。
オンライン学習のオープニングは特に重要
学習者は、オンラインコースにアクセスした最初の数分間に、それがどのようなコースであるか、つまり、自分の積極的な関与を必要とするインタラクティブなコースであるのか、ただ受動的に聞いていればよい面白みのないコースであるのかを判断してしまい、それがその後の行動に影響します。だからコースのはじめに学習者を何らかのアクティビティに関与させ、「これは双方向的で興味深いコースだ」いう印象を持たせることが重要です。
次回は、長い教室型研修をオンライン化することと、テクノロジーの使用についての部分を紹介します。
この記事も含め、アメリカのATD(Association for Talent Development)のサイトには、バーチャルトレーニングに関連してキュレーションしたリソースが公開されています(https://www.td.org/virtual-training)。
元の記事:
https://www.td.org/magazines/td-magazine/convert-your-classroom-training-to-virtual-training
関連記事:
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。