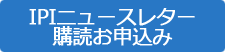以前のブログで、「スキルが低い人のほうが、スキルの高い人よりも自分の能力を高く見積もる傾向にある一方、スキルの高い人は、実際よりも自分の能力を低く見積もる傾向にある」こと(Dunning-Kruger Effect)に関する記事を紹介しました。
何かしらの専門分野を持っている人であれば、専門外の人から見当違いな意見をされて困った経験があると思います。学習の場面に限らず、このようなことも、「Dunning-Kruger Effect」の範疇に入ります。つまり、専門外の人は、「自分がその分野について知らないということを認識していない」ので、自分はわかっていると思いこんで意見を押し付けてくるのです。
今日紹介するのは、この「Dunning-Kruger Effect」について、学習心理学者のPaul A. Kirshner氏と職場の学習の専門家であるMirjam Neelen氏が書いたブログです。このブログを書いた両氏はもちろん学習の専門家なので、素人に見当違いな意見をされて辟易とする場面が多々あるようです。
Dunning-Kruger Effectとは、能力の不足している人(そのトピックに関する知識がない人)が、その知識のなさゆえに、自分の推論、選択、結論が誤っていることに気づかないことをいいます。つまり、知識(能力)の不足している人は、自分が何を知っており、何を知らないかを客観的に判断できないので、自分の能力を過大評価し、自分は非常に有能だと考えてしまいます。
学習や教育の世界にも、実際はそうではないにもかかわらず、自分は学習や教育についてわかっていると考えている人が大勢います。それは、誰もが学習や教育を経験しているので、その経験に基づいて学習や教育に関する意見を持っているからです。しかしそれは必ずしも、学習や教育に関して深い知識を持っていることを意味しません。
世の中には、学習に対する感情的な主張や、科学的根拠に基づかないソリューションがあふれています。学者として、学習に関する科学的な研究でわかっていることを一般の人に説明しても、見当違いな反論をされてしまいます。たとえば、「ハイライトをつける方法は効果が低い、非効率な学習方法である」と言うと、「ハイライトを使って試験に合格した知り合いがいるので、ハイライトが機能しないのはウソだ」という反論されるので、「そのようなやり方が必ずしも試験に合格した原因ではない」と説明しなければならないそうです。
自分の能力の低さを自覚していない人(つまりDunning-Kruger症候群にかかっている人)と議論する羽目になったときには、口をつぐむしかないようです。
元の記事:
関連記事:
『初心者には適切な指導者が必要(Dunning-Kruger Effect)』
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。