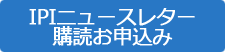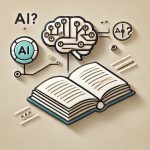研修後の「満足度アンケート」は、ほぼすべての研修で当然のように行われています。しかし実は、その運用次第では研修効果に害を与える可能性があります。「高評価を得た研修は成功」と思うことは自然ですが、それが必ずしも研修の効果、現場の変化につながるとは限りません。場合によっては満足度アンケートが逆効果となり、学びの価値を損なうことさえあるのです。こうしたことは、古くからの研究でも明らかになってはいるのですが、研修後アンケートは、依然として研修評価の方法としてこの業界に根付いてしまっています。
評価が低かった講師が、実は…
ある企業では、常に一貫して低評価を受けていた講師のことが問題となっていました。しかし研修後の学習成果を他の講師と追跡・比較したところ、実際にはこの講師が教えたグループが最も高い学習効果かったことが明らかになったそうです。しかも、この講師が低評価を受けていたのは、学習効果を高めるような方策をとっていたからだったのです。(Boehle, 2006)
学習は本来的に努力を要するもの
学習は、新しい知識を獲得し、習慣を変えるプロセスであり、その過程には困難や挑戦が伴います。この努力は、学びの深い定着に欠かせないものです。考えたり、時には失敗を経験することで、学びはより深く定着していきます。このように、学習が本来的に持つ困難さを克服することが、実際のスキルアップや行動変容に結びつくのです。上記の低評価の講師が行っていた方法も、学習者に負荷を与えるものであり、実はそれが学習効果を高めていたのですが、学習者にとってはそれが負担と感じられ、この講師への評価が低くなったのです。
満足度アンケートの結果を重視することの弊害
講師が評価を高めるために行うこと(面白い余談を入れる、早く授業を終わらせる、評価を甘くする、楽しいが無意味なゲームを取り入れるなど)は、実際には逆効果となる可能性があります。たとえば、面白い余談は、それに気をとられるあまり、本来学習に使うべき認知リソースをそのために無駄に使ってしまう可能性があります。こうした方策により高い満足度評価が得られれば研修が成功したかのように見えますが、それは単なる表面的な満足に過ぎないこともあります。
なぜこうなってしまうのか?
研修後アンケートの結果が、講師としての唯一の評価基準であれば、研修講師にとってアンケート結果は死活問題です。それゆえ、学習者からの高評価を得るため、学習効果よりも「楽しさ」や「雰囲気」に注力し、実際の学習内容やその後の行動変化のための対策がおろそかになったり、目先のテスト結果を向上させるための対策に終始し(結果つめこみ的になり)、長期的な学びを志向するマインドセットの醸成などがおろそかになったりする場合もあるでしょう。講師が「楽しい」ことや目先のつめこみを重視しすぎると、学びの深さや実際のスキルアップが犠牲になることがあるのです。
研修後アンケートの効果を高めるには?
では、満足度アンケートは全く無意味なのかといえば、そうではありません。適切に使えば有効に機能します。満足度アンケートは、研修の初期段階での参加者の意欲や感想を把握するためには有効です。ただし、それを唯一の指標にするのではなく、現場での行動変化や成果の向上といった次のステップもあわせて評価することが重要なのです。たとえば、研修終了後数ヶ月経った後に、上司から見て参加者の行動がどのように変わったかを追跡することで、実際の効果を測ることができます。このようにして、学びの目標を明確にし、その成果を適切に測定することで、研修の本当の価値を明らかにすることができるのです。研修直後のアンケートを唯一の評価指標としないことが重要なのです。
研修は、その後の適用(転移)があってこそ
たとえば中原淳氏は、「研修の満足度を問うな、研修転移を問え」と言っています。満足度評価は学習全体の一部を反映しているに過ぎません。研修本来の目的は学びを実際の行動に変え、ビジネス成果につなげることです。そのためには、満足度アンケートだけに頼るのではなく、多角的な評価を取り入れ、真に効果的な研修を目指す必要があるのです。