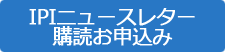John Medina氏は、分子発生生物学者であり、『ブレイン・ルール』という一般人向けに脳の仕組みをわかりやすく説明した著書によって広く知られています。今日は、そのMedina氏がATDに寄稿した記事を紹介します。
人が職場で学び、仕事をする方法に影響を与える5つのブレイン・ルール:
- すべての脳は、配線がそれぞれに異なる
人の脳の物理的配線は、何かを行ったり学んだりするにつれ絶えず変化しています。全く同じ脳を持った人は2人といません。個々の学習者、個々の従業員、個々の顧客の脳は、それぞれに配線が異なります。
- 人は退屈なものに注意を払わない
人は、自分の以前の経験に基づいて、何に注意を払うべきかを予想しています。人は特に、感情や脅威、今までに見たことのないものには注意を払うようにできています。
脳はマルチタスクを行うことができませんが、メール、電話、テキストメッセージなど、今の職場にはマルチタスクを助長するような要素があふれています。
- 記憶は薄れやすく、記憶を定着させるには繰り返しが必要
人の脳が短期的に保持することのできる情報はごく限られています。長期的に記憶するには、その情報を何度も繰り返す必要があります。何かを記憶したい場合には、それに関連する情報を心の中で繰り返します(たとえば、人の名前を覚えたいときには、その名前だけでなく、服の色などについても考える)。
- 人は長期的ストレスに耐えられない
人の脳は、30秒程度のストレスにしか耐えることができません。ストレスがそれ以上続くと、認知活動、運動機能、免疫機能などに悪影響を与えます。だから仕事で経験するストレスは、仕事のパフォーマンスに影響します。
- 人は、絶えず学び、探求するようにできている
人の探求意欲がなくなることはありません。特に乳幼児は、環境に対して受動的に反応するのではなく、観察し、仮説を立て、実験し、結論を出すという活発な試行を行っています。
このような探索的行動は、職場で高く評価される能力でもあります。利益を生むアイデアを一貫して思いつくようなビジョナリーは、以下のような特性(イノベーターのDNA)を備えています。これらに共通しているのは「探求欲」です。
- 並外れた関連付け能力があり、普通の人には思いつかないようなつながりを見出すことができる。
- 「もし~だったら?」、「なぜ~ではいけないのか?」、「なぜこの方法でやっているのか?」といった疑問を絶えず習慣的に考えている。
- あれこれと試し、実験したいという飽くことのない欲求を持っている。
元の記事:
https://www.td.org/insights/brain-rules-what-science-says-about-how-we-learn
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。