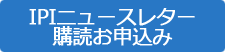しばらく前から、マイクロラーニングという言葉が聞かれるようになり、次第に職場にも導入されるようになっています。マイクロラーニングとは、小さな学習コンテンツや学習アクティビティを使って、短時間学習することです(micro=非常に小さい)。これには、人間の注意の持続時間が短いことや、人間は一度に大量の情報を処理することが得意ではないことなど、認知科学的な背景もあります。
今日紹介するのは、このマイクロラーニングが普及しつつある理由や、どのような場合にマイクロラーニングによる学習が適しているかの説明です。
世の中の進歩のペースが速まり、企業が成功するには従業員が新たな知識やスキルを迅速に身につけることが求められる一方、従業員は仕事に圧倒され、学習する時間がなかなかとれません。マイクロラーニングを導入すれば、モバイルデバイスで配信するなどして、忙しい人たちがちょっとした合間に学習することができます。
認知科学によれば、一度にすべてを学習してもすぐに忘れてしまう一方、時間をおいて何度も学習を繰り返した方が、長期的な記憶が向上します(分散効果)。マイクロラーニングは、小さい単位で学習を繰り返すのに適した方法です。
しかしマイクロラーニングは、どのような学習にも適しているわけではありません。単なる情報提供ではなく、深い知識やスキルの構築が必要とされる場合や、短期間で何かに上達する必要がある場合には、より本格的な学習ソリューションが必要となります。短い単位の学習だけでは間に合いません。
マイクロラーニングは、ちょっとした情報提供や、本格的な学習をする前の準備、学習中の強化、学習後のフォローアップなど、短い時間繰り返すことで学習を強化する手段として役立つと思われますが、この方法ですべての学習をまかなうことは難しいようです。
元の記事:
https://www.td.org/publications/blogs/learning-technologies-blog/2015/06/the-myth-of-micro-learning
関連記事:
マイクロラーニングの記事:
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。