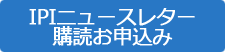今日は、忘却に関して科学的研究でわかっていることを解説した記事を紹介します。
エビングハウスの忘却曲線は、何かを学んでそのままにしておけば、急速に忘却が進むことを示したグラフです。エビングハウスは記憶を最初に研究した人であり、その研究は、1885年にさかのぼります。
エビングハウスは意味のない音節を暗記する方法で忘却率を測定しましたが、以降、忘却に関してさまざまな研究が行われ、忘却は、単に時間の経過と共に進むだけでなく、情報が学ばれた方法によっても忘却率が異なることがわかっています。意味のない音節を忘れることと、学習者にとって意味のあることを忘れることは、同じことではありません。
忘却が生じる主な理由のひとつは、「そもそも何も記憶していなかった」ことによります。何かを覚えるには、まず対象を知覚し、注意を払い、作業記憶で処理し、長期記憶にエンコーディングする必要があります。
いったん記憶しても忘れるのはなぜか?
記憶の科学によると、忘却は、「劣化」および「干渉」という2つの理由で生じます。
劣化とは、いったん記憶したことを後から使わないと、時間とともに薄れていくことを意味します。
干渉とは、類似の情報が記憶されているときに、それらにアクセスしづらくなることを意味します。
記憶のタイプ
研究によると、忘却のタイプは、最初にその情報が記憶された方法に大きく依存します。宣言的記憶(自分が覚えていることを表現できるタイプの記憶)は、親近性(familiality)または想起(recollection)いずれかの形式をとります。
親近性(familiality)に基づく記憶とは、何かに関する浅く漠然とした記憶のことです。想起(recollection)できるような記憶は、しっかりと詳細に覚えている記憶のことです。
親近性に基づく記憶と、想起可能な記憶は、異なる方法で脳に保存されています。
記憶の「干渉」に強いのは、想起可能な記憶の方ですが、劣化には強くありません。
つまり、以下のことを意味します。
- 深く学んでいないこと(親近性)は、簡単に忘れてしまう。
- 深く学んだ記憶(想起可能)は、干渉に強い。
- 深く学んだ記憶(想起可能)であっても、時間とともに劣化する。
- 劣化を防ぐには、その記憶を後から使ったり、思い出す必要がある。
元の記事:
https://isd.td.org/needs-assessment/what-do-you-know-why-do-people-forget-what-they-learn/
関連記事:
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。