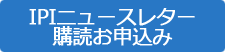認知心理学では、脳での情報処理の仕組みがコンピューターの情報処理に例えて説明されます。たとえば、作業(短期)記憶、長期記憶のように、RAMやハードディスクをイメージする用語が使われます。今日は、この脳での情報処理の仕組みについて解説した記事を紹介します。
認知に関して最も研究が進んでいる分野のひとつは、「記憶」についてです。認知心理学では、脳が情報を処理、保存する方法をコンピューターになぞらえて説明しますが、実際には、人の脳はコンピューターと同様に情報を処理しているわけではありません。
最近の研究では、記憶同士のつながり、その記憶の持つ価値、記憶を想起する頻度などによって、記憶が変化すると考えられていますが、脳の機能についての理解はまだはじまったばかりであり、神経科学(neuro~)や脳に基づく(brain-based~)学習といわれているものは、実際には認知心理学の成果に基づいています。
認知心理学は通常、認知を個人の観点から捉えます。学習を情報処理的に捉える方法は、個人の学習について理解したり、よいインストラクションをデザインする上で役立ちます。
しかし人間の思考について考えるときには、単に個人レベルでの知覚、記憶、想起だけでなく、社会的、文化的側面も考慮する必要があります。
たとえば職場では、職場に適合する方法、タスクのやり方、職場の社会的規範など、周囲の人から学びます。多くのスキルは、社会的コンテキストの中で学ばれるのです。だから職場の学習をサポートするには、個人の学習と、組織の学習の相互関係を理解する必要があります。
効果的な学習をデザインするには、個人と社会両方の側面から学習を捉える必要があります。
元の記事:
https://www.td.org/insights/what-do-you-know-do-our-minds-work-like-computers
関連記事:
『「脳に基づく(brain-based …)」学習は、事実というより虚構である』
『ブレインルール: 人がどのように学ぶか(how we learn)について科学が教えてくれること』
※このサイトに掲載されている一連の記事は、オリジナルの記事の全体または一部の概要を紹介するものです。正確なところはオリジナルの記事をご参照ください。